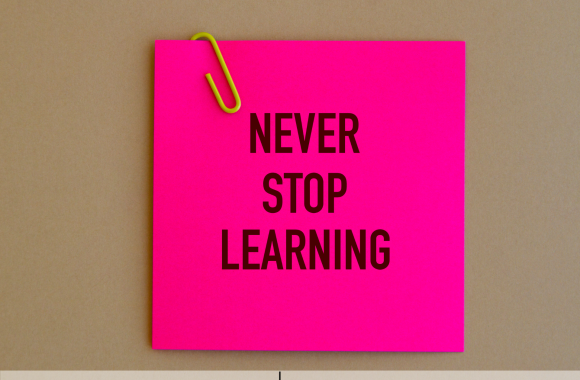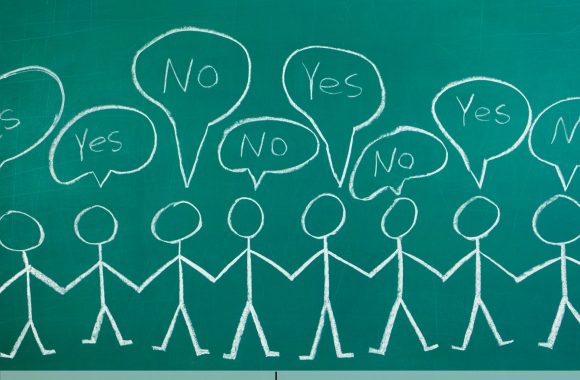ティーチングスキルとは(後半)

前回、教えるとは何か、また相手に教える時のさまざまな工夫について紹介しました。今回は、そこから一歩踏み出して「相手のやる気を引き出す方法」など、ティーチングを実践する際にすぐに使えるスキルをご紹介していきます。
目次
相手のやる気を引き出す方法

「頑張って教えても、相手がやる気を出してくれない…」そんな時におススメするのがARCS動機づけモデルです。
ARCS動機づけモデルとは
ARCSとは、Attention(注意)・Relevance(関連性)・Confidence(自信)・Satisfaction(満足感)の頭文字から取った言葉で、1983年、アメリカの教育心理学者ジョン・ケラー博士が提唱した学習者のモチベーションを高めるための理論です。4つの要素を意識しながら接していくことで、自然と「やってみよう!」というような前向きな気持ちで学べると言われています。教育現場だけではなく、企業での研修などさまざまな「教える」というシーンで活用されているARCS動機づけモデルの実践例を見ていきましょう。
ARCSを意識した声掛け例
・Attention(注意):「この方法を使うと作業時間が、実は半分になるんです」と意外性のある情報で興味を引く。
・Relevance(関連性):「〇〇さんの普段担当している業務でも、このスキルは使えますよ」と具体的な活用シーンを連想させる。
・Confidence(自信):「まずは簡単なところから一緒にやってみましょう」とスモールステップを踏んでいくことで、自信を持ってもらう。
・Satisfaction(満足感):「短時間ですごく上達しましたね」と進歩を認め、満足感や充実感を感じてもらう。
この4つポイントを意識するだけで、相手のやる気がぐっとあがります。
ロジカルに伝わる「学習デザイン」

先ほどのARCS動機づけモデルに続いて、初心者でも手軽に取り入れやすいのが、「どう伝えれば相手に伝わりやすいか」を考えて学びの流れを組み立てる「学習デザイン」です。学習デザインと聞くと難しそうだな…と感じてしまいそうですが、実は3つのポイントを押さえるだけで、とても効果的な学びをデザインすることができるのです。
ここでは、“資料作成をもっとスピーディ―にできるよう、後輩にテンプレート機能の使い方を紹介する”という場面を想定して具体的な実践の仕方を紹介します。
ポイント1:ゴール(目標)を明確にする
「今日は、資料作りをもっと早くできるように、テンプレート機能の使い方を紹介しますね」というように、最初に“何を学ぶのか”や“目的”をはっきり伝えることがとても重要です。そうすることで、相手は学ぶ理由を理解できて、内容がスッと頭に入りやすく、最後まで集中して取り組めるようになります。
ポイント2:理解度をチェックしながら進める
「分かりにくいことはありますか」など、相手がきちんと理解できているかを確認するための声掛けや、実際にテンプレートを開いて、作業をしてみてもらうといった工程を挟むことも大切です。“理解したつもり”を防ぐと同時に、やってみることで知識の定着にも役立ちます。
ポイント3:質問しやすい環境を作る
相手から質問が出たら、まずは肯定して安心感を与えましょう。「いい質問ですね」や「そこ、気になりますよね」というような共感のこもった言葉で返すと、相手が分からないことを素直に聞きやすい雰囲気になります。こういった学びの環境を作るのも学習デザインの一部です。
本格的にティーチングスキルを学ぶなら

いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した「ARCS動機づけモデル」や「学習デザイン」は、数あるティーチングスキルのほんの一部にすぎません。ですが、これらの知識を活用することで、教える力は格段に高まるはずです。「本格的に学んで業務に取り入れてみたい」と思った方も多いのではないでしょうか。
資格とキャリアのスクールnoaでは、ティーチングスキルの理論と実践の両方を学ぶことができる「ティーチングスキル講座」を開講しています。仕事でもプライベートでも使える“教える力”を、この機会に学んでみてはいかがでしょうか。
〜ティーチングスキルを体感できる無料セミナーも開催予定です。~
「教える」って、こんなに奥深い! ― 職場で活きる“ティーチング”を体感する90分 ―無料セミナー
※なお、先着20名となりますので、定員に達した場合にはご参加できません。